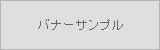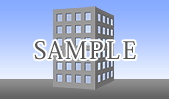松戸市の地理情報の最近のブログ記事
Flood Mapで将来の温暖化による海面上昇に備える
Flood Mapというサービスがあります。このサービスを使うと、地球温暖化の結果、自分の住んでいる場所があと何メートル海面上昇すると水没するのかが分かります。Google Mapsを使っているので衛星軌道からの写真と通常の地図表示の2パターンで検討可能です。

こちらが、海面が9メートル上昇した時の松戸市周辺の水没状況です。青くなっている部分が、水没するエリアです。やはり常磐線から左側はすべてアウトですね。。東松戸も、川が流れていることもあり、ずいぶん深くえぐれてしまうようです。

タグ
松戸市の洪水ハザードマップ
松戸市では、洪水ハザードマップを公開しています。これは、洪水のハザードマップです。
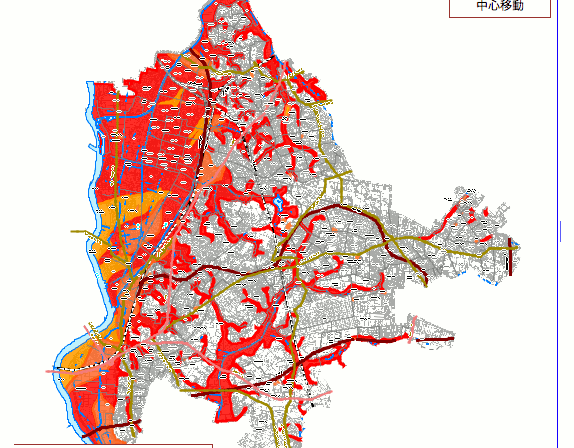
常磐線から左側、つまり江戸川沿いで低い地域がすべて水色になっていることがよく分かります。
下総台地内でも、川沿いや、21世紀の森公園の周辺など、水辺になっている地域一体も、ピンク色に囲われています。


また、地震が起きたときは液状化が非常に心配です。液状化とは、地震の際に地下水位の高い砂地盤が、振動により液体状になる現象で、これにより比重の大きい構造物が埋もれ、倒れたり、地中の比重の軽い構造物(下水管等)が浮き上がったりする。これは埋め立て地だけの問題だけではありません。
これが松戸市の液状化のハザードマップです。洪水のハザードマップの該当地域とほぼ同一ですが、さらに広い範囲が対象に入ります。
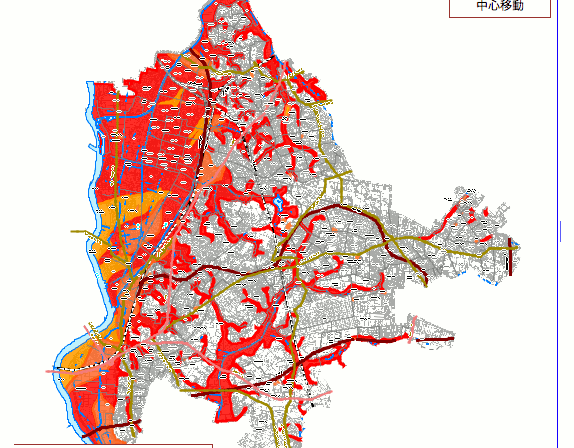
タグ
松戸市の地形
松戸市の地形は、常磐線を境に、西側に江戸川沿いの海岸低地と、東側の下総台地に大別されます。台地内には、小河川の影響による谷地が枝状に存在しています。
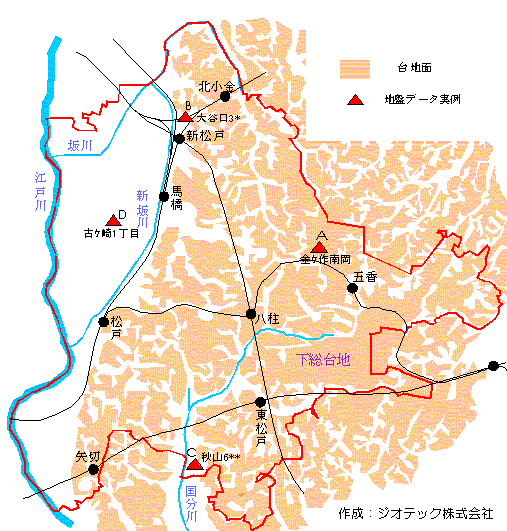
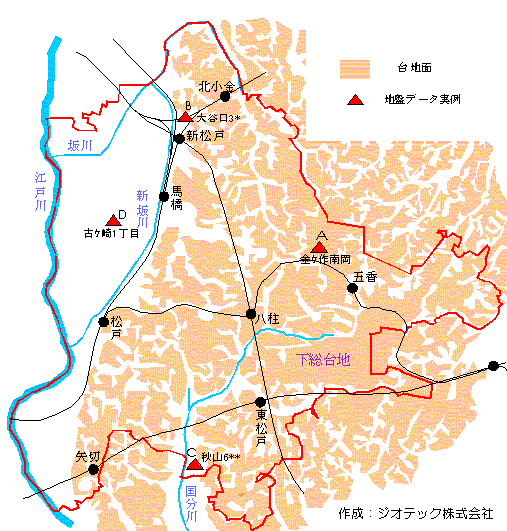
地形・地質と住宅地盤
・台地面
比較的海抜高度が高く起伏の少ない平坦面で、関東ローム層と呼ばれる火山灰土で覆われています。この関東ローム層とは、富士山や箱根の噴火で放出された火山灰が偏西風に乗って流れてきて、一万年以上もの長い時間をかけて、含まれている鉄分が酸化して 赤黒い土の層になった 土の層です。
関東ローム層は、上部のローム土(赤土)と下部の凝灰質粘土に大別されるが、自然堆積したローム土は、土を構成する粒子同士がくっつきあっていてるため、安定した住宅地盤になる場合が多い。ただし、下部の凝灰質粘土は部分的に軟弱になっていることがあるので、ローム土が薄く、凝灰質粘土が浅く分布している場合には、基礎補強対策が必要となることがある。
・谷底低地
台地部が小さい河川などによって削られて形成された低地で、台地部の間に樹枝状に分布している。台地を形成していた土砂が再堆積した土や有機質土(腐植土)などが分布しており、非常に軟弱な地盤となっている。有機質土は、有機質を5%程度以上含む酸性の土で、中和反応によりセメント系固化材が固まりにくいという特徴があります。そのため、長期的な沈下(圧密沈下)を防止するような基礎補強策が必要となることが多い。
・海岸低地
東京湾沿岸に広く分布する標高の低い平坦面である。地下水位が高く、上部には緩い砂や軟弱なシルトなどが分布しているため、標準的な基礎では、十分な耐力を確保することが困難であり、適切な基礎補強策が必要となる。
タグ
松戸市の災害危険区域
松戸市で一軒家の購入を考える上で、絶対に外せないのは、 江戸川の存在だ。
江戸川は、利根川から分かれ東京湾に注ぐ延長約60kmの首都圏を代表する河川。流域面積は約200km2と、川の規模の割には大きくないが、利根川の洪水の分派と首都圏の水源河川、広大な自然とレクリエーション空間として大きな役割を担っている。
左岸側は下流部を除いてほぼ沿川地域まで台地が接近しているのに対し、右岸側は全川にわたり低地が広がっている。
 また、沿川地域は、両側ともに市街地が多く、特に下流部は人口、資産が高度に集中している。このため、江戸川が計画規模を上回る洪水などにより破堤した場合の洪水氾濫危険区域は全体で約500km2、危険区域内の世帯数は約80万世帯、人口は約250万人と想定されている。
現在の江戸川で、各沿川市区町で堤防が壊れた場合のシミュレーション結果を包括したもの。
また、沿川地域は、両側ともに市街地が多く、特に下流部は人口、資産が高度に集中している。このため、江戸川が計画規模を上回る洪水などにより破堤した場合の洪水氾濫危険区域は全体で約500km2、危険区域内の世帯数は約80万世帯、人口は約250万人と想定されている。
現在の江戸川で、各沿川市区町で堤防が壊れた場合のシミュレーション結果を包括したもの。

 また、沿川地域は、両側ともに市街地が多く、特に下流部は人口、資産が高度に集中している。このため、江戸川が計画規模を上回る洪水などにより破堤した場合の洪水氾濫危険区域は全体で約500km2、危険区域内の世帯数は約80万世帯、人口は約250万人と想定されている。
現在の江戸川で、各沿川市区町で堤防が壊れた場合のシミュレーション結果を包括したもの。
また、沿川地域は、両側ともに市街地が多く、特に下流部は人口、資産が高度に集中している。このため、江戸川が計画規模を上回る洪水などにより破堤した場合の洪水氾濫危険区域は全体で約500km2、危険区域内の世帯数は約80万世帯、人口は約250万人と想定されている。
現在の江戸川で、各沿川市区町で堤防が壊れた場合のシミュレーション結果を包括したもの。 
この氾濫危険区域図が示すように、ひとたび江戸川の堤防が破堤した場合、特に右岸地域でその被害が甚大になると予想されている。
これは、左岸側に比べ右岸側は平坦な低地が多く、破堤箇所にかかわらず氾濫による被害が広範囲に及ぶこととなるからだ。
困った事に、松戸のエリアで土地や分譲を探してみると、価格的にお手頃な物件の多くは、6号線と江戸川の間のエリアが非常に多い。確かに安さは魅力だが、万が一江戸川が決壊したら...それを考えると、とてもではないが自宅を購入する気にはならないですね。